この記事では初心者でも抑えておきたい「バラの病気について」と「害虫対策」についてご紹介しています。
バラと病気・害虫は切っても切れないものですが、それほど怖いものではありません。
基本的な対処法を知って上手に付き合っていきましょう。
バラ初心者が抑えておくバラの病気と対策
バラは花を咲かせるために、常にたくさんのエネルギーを使っています。
そのため、肥料を与えないままでいると株が弱り、必然的に病気にかかりやすくなってしまいます。
開花時は、咲き終えた花をこまめに切り落とし(花がら摘み)、余計な体力は使わせないようにながら正しいタイミングで追肥をして、あなたのバラが病気に耐えられるように元気な株にしておきましょう。
*追肥のタイミングについての記事もご参考になさってください。

バラの病気と害虫対策に初心者が持っておきたいアイテム

この2つはスプレー式ですぐに使えて、しかも予防と治療の両方をを叶えてくれます。
使い方は簡単で、「バラの様子がおかしいぞ!」と思ったら、さっと吹きかければいいだけです。
このとき注意したいのは、葉の表だけではなく、特に葉裏にしっかり薬剤を吹きかけること。
とはいえ残念ながら、 薬剤は被害をそれ以上広まるのを防いでくれることがメインで、これを散布したからと言って病気が完全に治ることはないと思っていてください。
ただ、完全には治りませんが、だからといってバラが枯れてしまうこともないので安心してください。
バラを始めたばかりで病気や害虫が心配なときは、【ばらのうどんこ病と黒星病に】と【ばらの害虫と病気に】この2つを用意しておけば大丈夫です。
続いて、たくさんの種類の病気や害虫被害の中で、特によくかかる病気と発生いやすい害虫について、2つずつご紹介していきますので、ご参考になさってください。
黒点病(黒星病)

黒点病はバラの葉に黒い点々ができる病気で、必ずかかる!と言っても過言ではない病気です。
この病気は土中にすむ黒点病に細菌が、水やり時や雨水で跳ね返りおもに葉裏から感染します。
こんな葉を見つけたら、すぐに取り除いては裏を中心に薬剤をかけてあげます。
ただ、急激に葉の量が激減するとバラがビックリしたり光合成の力が弱まるので、気をつけましょう。
私たちにできることは、水やりのとき土が跳ね返らないように、そして葉に水が駆らないよう土に近い低い位置からそっとあげることです。
黒点病はバラとセットのような病気です。あまり神経質にならずに、薬剤を使いながら上手に付き合っていきましょう。
うどん粉病

うどん粉病は葉や蕾に粉が吹いたようになってしまうカビの病気です。
この病気は、菌が風に乗ってやってきてかかってしまうので、予防がほとんどできません。
見つけたらすぐに病気の葉や蕾は取り除き、薬剤を3~4日感覚で数回まきましょう。
また、風通しが悪いと速いスピードで広がってしまうので、葉が込み合いすぎていてるところがあったら、葉を少しかっとして風通しを良くしてあげるのも大切です。
この”うどんこ病”も良くかかる病気ですので、見つけてもあわてず病気の葉を取り他に移らないようにして、薬剤を散布すれば大丈夫です。
アブラムシ

アブラムシの発生も黒点病と並ぶくらい頻繁に見られます。
特に新芽や柔らかい葉、蕾のまわりにビッシリいたりします。
放置するとまたたく間に増えてしまうので、見つけたらティッシュなどで取り除き、そのあとで薬剤を散布しておきましょう。
蕾のあたりに小さなプチプチが出来ている?と思ったらよく見てください!アブラムシかもしれません!
アブラムシは樹液を吸ってバラを弱らせるので、見つけたら早めに取り除いてくださいね。
チュウレンバチの幼虫

鉢の下に黒い点々が落ちていたり(チュウレンバチのフンです)、葉脈だけが残った状態の葉を見つけたら、チュウレンバチの幼虫の仕業かもしれません。
付近をよく見て、1枚の葉に3ミリ程度の幼虫が集団でいたら、葉を食べつくされる前にすぐにティッシュなどで取り除きましょう。
心配でしたら、その後に薬剤を散布しても構いません。
チュウレンバチの幼虫は風に乗って飛んでくるので、完全に駆除することは難しいですが、水をあげのとき明らかにおかしな葉があったら、まわりにいないかよく観察してあげてください。
まとめ
バラを育てていれば、病気や害虫はつきものです。
まず、株自体を健康に保たせるため、時期に合った追肥をしてあげるて病気に強い状態にしてあげましょう。
そして、いざという時すぐに対応できるように薬剤を用意しておくと安心です。
病気になっても害虫被害にあったとしても、放置しない限りバラが枯れてしまうことはありません。
あまり神経質にならずに、上手く付き合っていけたらいいですね。
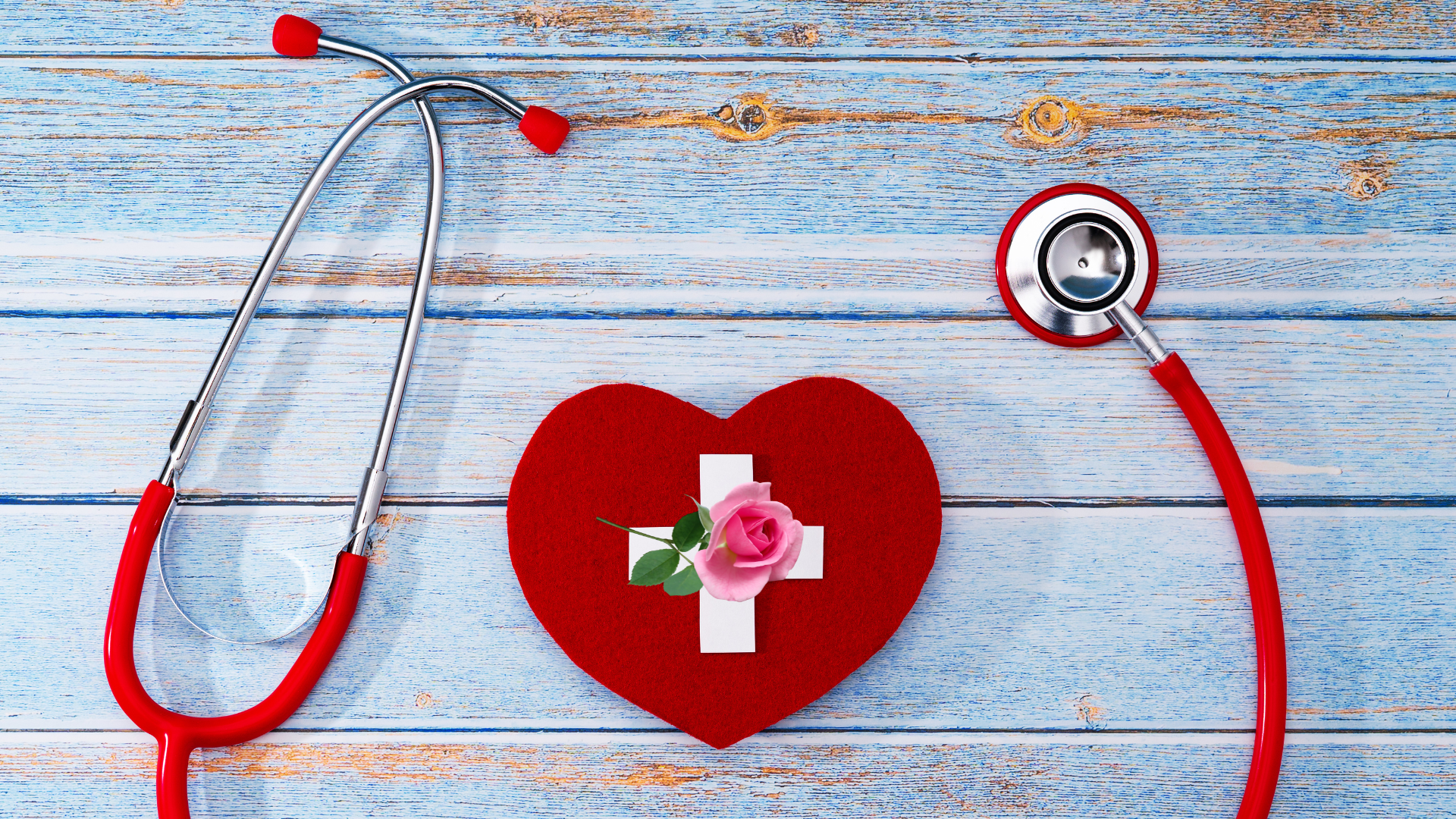







コメント